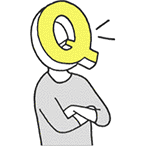
同胞生活
Q&A
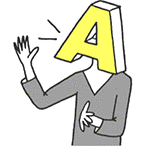
結婚・出産・子育てについて
新居に引っ越すとき・・・住所の届け出
新しく住まいを設けたり、引越しをする場合は市区町村役場に届出を行わなければなりません。
転出届
他の市区町村に引越しをするときに、これまで住んでいた役場で行います。引越しの1 か月前から届け出ることができ、その時、本人確認書類と印鑑が必要です。その際、「転出証明書」を交付してくれます。
転入届
引越しをした後(新しい場所に住みはじめた日)から14 日以内に、引越し先の市区町村役場で行います。前の住所地の市区町村役場でもらった「転出証明書」、本人確認書類、印鑑、特別永住者証明書・在留カード(*海外から引越してきた場合はパスポートも)などが必要です。
海外転出届
海外に滞在する場合、短期間でまた元の場所に戻るのであれば必要はありません。1 年以上、長期に海外に生活拠点を移す時に行います。国民健康保険に加入している人は、海外転出届を提出すると同時に国民健康保険から脱退します。国民年金は、海外居住者は任意加入ですが、保険料を納付することで継続することも可能です。
届出は出国前に行います。本人確認書類、印鑑、国民健康保険証、国民年金手帳などが必要になります。届出をせず海外に長期滞在すると、その間の健康保険税や年金保険料が未納・滞納扱いになるので注意が必要です。
[ワンポイント] 転居届とは
同じ市区町村内で引越しをする際に行うもので、引越しから 14日以内に行います。
[ワンポイント] 罰金があります!
転出・転入・転居のいずれの場合も、届出を怠ると、入管特例法または入管法による罰則規定により、20万円以下の罰金が科されます。
日本人の場合、このような届出をしなかったり、うっかり遅延したりすると5万円の過料という行政罰が科されることがあります。
外国籍の場合はこの過料に加えてさらに上述の入管特例法または入管法による刑事罰が加重され、非常に不当な取扱いとなっています。特別永住者ではなく、在留カードを持っている中長期在留者の場合、住所地の届出などが14日以上遅延すると 20万円以下の罰金で、90日以上遅延すると在留資格の取消事由になるので注意が必要です。
子が生まれたら
在留資格の取得手続き
父母がともに外国籍の場合、先ほどの出生届の他に子の在留資格の取得手続きが必要です。父母の一方が日本国籍の場合は不要です。
父母またはその一方が特別永住者の場合、出生した日から60 日以内に出生届を出した市区町村役場で「特別永住者資格取得申請」ができます。
父母がともにその他の在留資格(中長期在留者)の場合は、30 日以内に最寄りの地方入国管理局で、子の在留資格取得申請を行います。
児童手当
日本国内に住所を有し中学校卒業までの子を養育している者に支給されます。特別永住者証明書、在留カードがあれば対象になります。
父母または養育者が複数いるときは生計を維持する程度が高い者に、父母が別居している場合は、子と同居している親に支給されます。住民登録をしている市区町村役場で、出生届と同時に手続きをしましょう。
出産育児一時金
健康保険に加入している人(被保険者とその被扶養者)が子どもを産んだ時、申請により 1人につき 42万円が支給されます。妊娠 12週目以降に死産をしてしまった場合も対象になります。国民健康保険に加入している人は市区町村役場で、その他の公的保険は職場で申請します。
妻が外国籍で、母国に里帰りして出産をしたときも対象になります。その場合、病院での出産証明書などが必要になります。忘れずにもらっておきましょう。
同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子
子の姓(氏)
同胞と日本人の夫婦の間に生まれた子は、出生届の提出により日本人の親の戸籍に記載されます。そのため日本人の親の「氏」となります。
子に同胞の親の「姓」を受け継がせたい場合、日本人の親と子が一緒に、または子のみ、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」を行うか、法務局で子の日本国籍離脱手続きを行います。
子のみが家庭裁判所で「氏の変更の申立」をした場合、子は日本人の親の戸籍から「除籍」され、子を筆頭者とする戸籍が新しく編製されます。さらに子が生まれ、上の子と同様に「氏の変更の申立」をする場合、兄弟姉妹それぞれ単独の戸籍が編製されることになります。
子の国籍
子は父母両方の国籍を受け継ぎ重国籍です。22 歳(※2022年4月からは日本の国籍法は20歳までとなった)までに父母のいずれかの国籍を選択する必要があります。
朝鮮・韓国籍を選択する場合、日本国籍離脱手続きを行います。子が15 歳未満の場合は、親権者が行うことができます。国籍離脱手続きは、住所地を管轄する法務局で行います。
手続きが完了すると、在留資格の取得手続きを入国管理局で行います。朝鮮・韓国籍の親が特別永住者の場合、子は特別永住者となります。
同胞と国籍
日本人やその他の外国籍の人との国際結婚が増加する中、同胞法律・生活センターに寄せられる相談には、配偶者やその間に生まれた子の国籍がどうなるのかというものがあります。
在日同胞の場合、①本国が南北朝鮮の「分断国家」で、②一方の朝鮮民主主義人民共和国(以下共和国)を日本政府が承認せず、さらに③「未承認」を理由とした差別的行政により、同胞の国籍問題は他の外国籍の人に比べると複雑です。
そもそも国籍とは、「ある国の構成員、あるいは国民(公民)たる資格」で、誰が国民であるかを決定するのはその人が属するとされる国の法によります。国籍の決定は主権に関わる国内管轄事項というのが国際法上の原則です。ある人が日本国籍を持っているかどうかは日本国籍法が、フランス国籍を持つかどうかはフランス国籍法が決定するのです。
したがって、在日同胞の国籍は日本の国籍法は勿論、ましてかつての外国人登録法によって決められたものではありません。現在、特別永住者証明書や在留カード上の記載が「朝鮮」であれ「韓国」であれ、それは日本の法律によるもので、その記載のいずれかでその人の国籍が決まるのではありません。「朝鮮」だから朝鮮民主主義人民共和国の、「韓国」だから大韓民国の国籍を持っていると理解している人も少なくないようですが、それは間違いです。
では、特別永住者証明書などの国籍欄に記載された「朝鮮」「韓国」という表示は何なのか?周知のとおり、この「朝鮮」「韓国」という表示は日本政府によって恣意的にもたらされた経緯があります。
かつて植民地支配期から1945年の解放を経て、1952年のサンフランシスコ講和条約発効まで、在日同胞は「日本国籍」とされていました。しかし実際には、1947年に「外国人登録令」が実施され、その当時の登録の国籍欄には「朝鮮」と記載されました。その後1948年に共和国、大韓民国が設立され、朝鮮半島の分断後も国籍欄の記載は「朝鮮」でした。1950年に駐日韓国領事部の要請を受けてGHQが日本政府に対し「韓国への書換えを認めるよう」覚書を出し、「本人の希望によって韓国または大韓民国と記載しても差し支えない」とし、他方で「朝鮮民主主義人民共和国と記載するよう申請があっても一切応じないこと」という取り扱いをしたのです(民事局長通達554号)。
1965年韓日条約による韓日法的地位協定では、外国人登録上「韓国」と表示されている同胞にのみ協定永住権を付与するという非常に差別的な取り扱いを行いました。さらに①「韓国」表示のみを国籍とし、②「朝鮮」表示は「符号」とみなす、さらに③すべての在日同胞の国籍問題の処理については一律に大韓民国国籍法が適用されることになりました。すなわち日本国内では「韓国」表示のみが国籍として通用するようになったわけです。
在日同胞の国籍の扱われ方にはこのような歴史的経緯があります。本国の南北分断という現実や日本と南北朝鮮の政治関係を背景に、このような日本政府(かつての外国人登録法)による国籍欄の差別的な分断表示が同胞社会の分断とさらには個々人の本国への帰属意識をも分断してきたように思います。
在日同胞の国籍の認定は、共和国国籍法が承認され、私たちが持つ共和国の国籍証明書や共和国旅券、あるいは韓国旅券や在外国民登録などに基づいてなされるべきなのです。
どうなる同胞の子の国籍、日本国籍離脱手続き
同胞と日本人の間に生まれた子の国籍はどうなるのでしょうか?下記のとおり、5つのケースに分けて説明をします。
ケース(1) 父-日本国籍、母-「朝鮮」籍の場合
子は日本と「朝鮮」の重国籍です。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。子を母とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
●国籍離脱申請手続き
国籍離脱の申請手続きに必要なものは次のとおりです。
-国籍離脱届(申請窓口に備置されています)
-離脱者(子)の戸籍謄本
-母親の特別永住者証明書または在留カード、住民票
-離脱者(子)の住民票(子が15歳未満の場合、法定代理人あるいは親権者による届出になるので、その資格を有する書面)
-印鑑
以上の書類が受理されると、数週間後に法務局から(国籍離脱の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持参して、最寄りの市区町村役場の戸籍課にて国籍喪失届を行い、入国管理局で在留資格取得手続きを行います。
ケース(2)父-日本国籍、母-「韓国」籍の場合
子は日本と「韓国」の重国籍となります。
出生届の提出により、父が日本人ですから日本国民として取り扱われ、父の戸籍に記載され、父の日本姓を名乗ります。
子を母とおなじ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース(1)と同様です。
ケース(3)父-「朝鮮」籍、母-日本国籍の場合
子は「朝鮮」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の朝鮮姓を名乗ることはできません)
子を父とおなじ「朝鮮」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。
*子は在留資格を取得し、特別永住者証明書または在留カードの交付時に、父と同じ朝鮮姓にすることができます。
ケース(4)-「韓国」籍、母-日本国籍の場合
子は「韓国」と日本の重国籍です。
しかしながら、出生届の提出により母が日本人ですから日本国民として取り扱われ、母の戸籍に記載され、母の日本姓を名乗ります。(*子は父の姓を名乗ることはできません)
子の国籍を父と同じ「韓国」籍にするためには日本国籍を離脱しなければならず、最寄の法務局または地方法務局の国籍窓口で国籍離脱の申請手続きを行います。
国籍離脱の申請手続きはケース①と同様です。
ケース(5) 父母がともに同胞で、国籍表示が異なる場合
たとえば、1)父-「朝鮮」、母-「韓国」、2)父-「韓国」、母-「朝鮮」の場合、このような同胞同士のあいだに生まれた子については、子の国籍を朝鮮、韓国のいずれの表示にするかは親の選択によるという取り扱いをしています。ですから、親の意向によって子の国籍は朝鮮、韓国のいずれの表示にもできることになります。
進学・キャリアアップについて
奨学金を利用する
奨学金とは進学を希望する学生が、家庭の経済的理由で進学をあきらめることのないように、公的な機関 (国や地方自治体)や民間団体が進学に必要な金額の一部、もしくは全額を支援する制度のことです。奨学金は返済が不要の給与型と、返済が必要な貸与型の2種類に大別され (一定の条件をクリアすると返済が免除される貸与&給与型もあります )、さらに貸与型には返済金に利息が付かないものと、利息が付くものがあります。
金融機関が取り扱う「教育ローン」や地域の社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金(入学時に必要な費用のための就学支度費と月々の奨学金に相当する教育支援費の2種類)」も奨学金の一形態と言えますが、世界的には奨学金とは返済義務のない給与型奨学金のみを指すのに対し、日本における奨学金はほぼ全てが貸与型です。つまり、借りた全額を将来的に返済 (返還)することを前提に奨学制度を利用することが重要です。
[ワンポイント]日本学生支援機構の奨学金
日本学生支援機構 (JASSO)は2004年に日本育英会などの5つの法人が合併して設立されました。貸付の対象は大学・大学院・短大・高専・専門学校生であり、2016年度は132万人に対して 1兆944億円が貸し出されており、実に大学生の2.6人に1人 (38.5%)が奨学金を利用しています。無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金 (上限は3%)に加え、日本の大学に在籍しながら海外の大学に留学する場合の支援制度もあります (月額6~10万円、留学先の地域等により決定、8日以上1年以内、返済義務なし。貸与もあり)。
また、2018年度からは給付型奨学金が本格導入されます (主に低所得世帯の大学生が対象、月2万~4万円を給付、1学年あたり2万人程度を想定し、財源は200億円程度を見込む。2017年度は、一部対象者に先行実施された)。
一方、返済滞納者や連帯保証人に対する訴訟も社会問題化しており、貸与型奨学金は「教育ローン」であるとの側面も留意すべきです (「申請主義」ではあるものの、返還免除等の救済措置もあります)。
同胞学生を対象にした奨学金
| 名称 | 制度概略 |
| 在日本朝鮮人教育会 | 【給付型奨学金】 大学学部 1 年生及び専門学校生に月額 1 万円、大学学部 2 年生以上に月額 1.5 万円を支給。 |
| 在日朝鮮学生支援会 | 【給付・貸与型 ( 無利息 ) 奨学金】 学部生は給付型 (「金剛保険奨学金」。年額上限は 48 万円 ) 及び貸与型 ( 卒業年度生は年額 48 万円、卒業年度生以外は年額 24万円 )、大学院生は給付型 ( 年額上限は 36 万円 )。その他に高校生を対象とした給付型 ( 年額 12 万円 ) もあり。 |
| ミレ教育財団 | 【給付型奨学金】 東日本地域に所在する朝鮮・韓国語で普通教育を行っている教育施設等で学ぶ者を対象に月額 1 万円を支給。 |
| 在日コリアン支援会 | 【給付型奨学金】 京都在住で日本の高等学校またはこれらに類する課程の朝鮮・韓国語教育施設に通う者を対象に、月額 1 万円を支給。 |
| NPO 法人 ウリハッキョ | 【給付型奨学金】 弁護士を目指すために法科大学院に在学・卒業した者を対象に、月額 2 万円を支給。また、在日同胞社会の次世代を担う意欲のある若者の専門知識・技能や資格取得費用を支援する「チャレンジ型若手同胞人材育成事業」も整備。 |
| 成和記念財団 | 自然科学に関する研究を行う主として在日コリアン(特別永住者および永住者)の大学院博士課程は 70 万円、修士課程は 30万円(いずれも在籍またはそれに相当すると認められるもの)を応募論文の選考を経て助成。 |
※詳細な募集要件等は各団体のホームページを確認してください。規模が一番大きい朝鮮奨学会(現時点では民族学校在校者は対象外)のホームページもご覧ください。
国家試験の受験資格をめぐるあれこれ
同胞が活動する場は、日本国内はもとより海外にまで広がっています。法律、医療・福祉、工業・技術、土木・建築など、多様な分野で国家資格を取得して活躍する人たちが増え、根強い民族蔑視により職業選択の幅が狭められていた一昔前とは隔世の感があります。
日本には、国家試験による資格は公的な各種の検定なども含め約1500 種類以上もあるそうです。受験資格には、司法書士、弁理士、行政書士や宅地建物取引主任のように学歴、職歴、年齢など制限が無いものもあれば、大学、高校、短大などを卒業していなければならないという学歴やその分野での実務経験年数、年齢による制限など、資格により様々な制限があるものがあります。
これらだけでなく、これまで朝鮮学校は「各種学校」との理由からその卒業資格や履修科目が認められず、受験資格が認められなかったものがあります。かつて朝鮮大学校卒業生には、その卒業資格では税理士、社会保険労務士の受験資格が認められず、また保育士試験は一般の短大のように
2 年在学時に「卒業見込み」で受験することができませんでした。しかし、差別の是正を求める同胞の粘り強い運動の結果、税理士は朝大在学時(日本の大学同様一定の要件あり)に、社会保険労務士は卒業生に、保育士は「卒業見込み」の2 年時に受験資格が認められるようになりました。
保健医療や福祉分野では、養成校で所定の科目の履修後に受験資格が認められるものが殆どです。ここでは、その養成校への入学資格が「各種学校」との理由から朝鮮学校卒業生には制限されていたところ、2003 年10 月厚生労働省課長通知「福祉分野における各資格の受験資格等に係る各種学校の入学資格等の取扱いについて」により、入学資格の有無は各養成校の個別審査によるものとされました。その結果、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、
介護福祉士、言語聴覚士など広い分野で資格取得の途が開かれています。
とは言え、資格の種類は多く、受験資格に設けられる要件や制限も様々。朝鮮学校卒業生がチャレンジしたことのない分野もあるはず。センターにも「養成校への入学資格が無い」との相談が寄せられ、はじめてそのような資格を知ることも多いです。卒業資格を理由に受験資格や入学資格が認められないようなことがあれば、すぐにご相談ください。
在留資格について
16歳になったら・・・特別永住者証明書など
2012年7月に外国人登録制度が廃止され、新在留管理制度が施行されています。特別永住者には特別永住者証明書が、それ以外の中長期在留者には在留カードが交付されるようになりました。16歳未満の者は16歳の誕生日までに、更新の手続きが必要です。かつての外国人登録証の時代には、16歳未満の者は16歳の誕生日の前後1カ月の間に住所地の市区町村役場で更新ができましたが、新制度では、誕生日の当日までに、特別永住者の場合は市区町村役場で、永住者の場合は地方入国管理局で更新をしなければなりません。
とりわけ、16歳未満の者の場合、誕生日前日までは親権者が本人に代わって行なわなければならず、本人が手続きできるのは誕生日当日のみとなります。また、更新手続きが遅れると、未成年者であるにもかかわらず「1年以下の懲役または 20万円以下の罰金」という罰則が設けられています。抗議の末、誕生日の 6カ月前に更新の通知が法務省から送付されるようになったものの、罰則は改正されておらず、注意が必要です。
特別永住者証明書、永住者の在留カードの有効期間は 7年で、次回以降は、特別永住者は7年ごとの誕生日までに、永住者の場合は入管で在留カードの期間更新をした日から7年ごとに更新を行います。
[ワンポイント] 入管法上の罰則制度
入管法が「改定」され新在留管理制度が施行(2012年7月9日)されています。「改定」とは言え、かつての旧外国人登録法にあった刑事罰による罰則制度はそのまま引き継がれています。
「特別永住者証明書」の7年ごとの更新については、更新期限が超過してうっかり手続きを忘れたという場合でも、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
その他、「特別永住者証明書」の受領拒否、提示拒否や、紛失した場合の再交付手続きの遅延の場合も同様に1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、住所地などの届出の遅延などの場合は20万円以下の罰金が科されます。
さらには、住所地の届出、すなわち引っ越しをした際の転出・転入届など、住民基本台帳上の届出をうっかりした場合、行政罰としての5万円の過料に重ねて上記の罰金が科されることになります。
このように罰金刑等の刑事罰は依然残されたままとなっており、外国人を治安管理の対象とみる日本政府の姿勢に変わりはありません。
特別永住者ではない他の中長期在留資格で「在留カード」を持っている人の場合、住所地の届出等が14日以上遅延すると20万円以下の罰金で、90日以上遅延すると在留資格の取り消しとなります。なので、永住者資格を持っていても在留資格が取り消される可能性があります。
配偶者の離別や死別等の届出(日本人あるいは永住者の配偶者等の在留資格の場合のみ)や所属機関の変更やが14日以上遅延すると20万円以下の罰金。また、就労許可の無い外国人を雇用した場合、就労許可が無いことを知らなかった場合であっても、雇用主は不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)に科せられます。
このように厳格な罰金制度と在留資格の取り消し事由がありますので、注意が必要です。
海外に行くとき・・・再入国許可
同胞が海外に出かけるときは、その目的が旅行であれ商用、留学であれ、必ず入国管理局で再入国許可を取得しなければなりません。新在留管理制度では、特別永住者の再入国の有効期間は6年(数次)に伸長され、新しく「みなし再入国許可制度」が導入されています。
有効な旅券と特別永住者証明書または在留カードを所持して出国する場合、特別永住者証明書を持つ同胞は日本を出国後2年以内に、在留カードを所持する中長期在留者は1年以内に再入国する場合は、別途再入国許可を受けなくてよいという制度です(*出入国時の審査の際、特別永住者証明書・在留カードの提示を求められます)。
「有効な旅券」とは「日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券」とされているため、韓国旅券を所持する人はこの制度を利用できますが、朝鮮籍同胞の場合、不当にもこの制度を利用できず、従来どおり、入管で再入国許可を受けなければなりません。
みなし再入国許可制度で出国した場合、必ず出国の日から2年(もしくは1年)以内に日本に再入国しなければならず、渡航先での期限の延長は、天災や病気・事故など、いかなる理由があっても一切認められません。期限を超えると、出国時に遡って日本における在留資格を喪失します。長期間海外に出かける時は、面倒でも入管で数次の再入国許可を受けて出国することをおすすめします。
[ワンポイント] 特別永住者とは?
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者とその子孫」のことです。要するに戦前に来日し、戦後も引き続き在留している旧植民地出身者とその子孫に限って、特別に認めた在留資格のことです。解放後いったん本国に戻り、また来日(1945年 9月3日以降)した人は対象外となり、特別永住者資格を取得できません。
外国人を雇用するとき・・・就労と在留資格
「外国人を雇用したい」「韓国の親族を雇用したい」、このようなケースも最近多いのではないかと思います。実子以外は、目的に準じ在留資格(いわゆるビザ)を取得し、日本に呼び寄せなくてはなりません。
例えば、焼き肉店の調理師として雇用したい場合、「技能」の在留資格を取得しなくてはならず、10年以上の勤務経験が必要です。
在日同胞が韓国同胞や外国人を雇用する場合、「技能」(外国に特有の料理~韓国料理など、外国に特有の製品の製造、宝石・貴金属・毛皮の加工の技術など)「技術・人文知識・国際業務」(翻訳・通訳、広報、宣伝、又は海外取引業務、デザイン、商品開発など)が主な在留資格となりますが、大学卒業資格や、国際的な資格、10年以上の勤務経験などの条件が課されています。このような在留資格以外の人、そもそも在留資格の無い人を雇用した場合、違法となり、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます。この場合、雇用主が永住者であっても、退去強制となり得るので、十分に注意して下さい。
[ワンポイント] 資格外活動(アルバイトなど)の注意
「留学」や「家族滞在」の在留資格では、資格外活動の許可を得ることで、週
28時間の労働が認められます。例えば 1日
4時間で 7日間、5時間で約5日間のアルバイト、パートが可能です。事前に入国管理局で、資格外活動の許可を必ず受けておく必要があります。本来、「留学」は、勉強をするために来日しているので、労働は禁止されています。ですので、許可なく労働した場合、本人のみならず、当然雇用主にも罰則があります。ただし、夏休み等の長期休暇の期間は、1日8時間の労働が認められます。
焼肉店や居酒屋などでは最近アルバイトも不足しているようで、外国人の方がまじめに一生懸命働くと評判は良いようです。しかし、違法な低賃金で使用した場合なども、雇用主側に罰則(労働法)がありますので、要注意!
[ワンポイント] ワーキングホリデイ
2国間の協定に基づいて、青年(18歳. 25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度です。期間は通常1年、比較的広域な職場(単純労働も可)で就労することができます。
協定国との間で利用ができ、ちなみに韓国との協定国は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾(中華民国)、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペインとなっており、英語圏の国を1年ずつ 3カ国(例:カナダ、イギリス、オーストラリアなど)ワーキングホリデイを利用すれば、3年間収入を得ながら英語を習得でき、今後の就職にも有利になり得ます。
[ワンポイント] 家族の呼び寄せ
外国人が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在」の在留資格となりますが、これは未成年で被扶養者である子、配偶者のみが取得できる在留資格です。それ以外の親、兄弟等はその資格で入国することはできません。
この場合、各々が個別に在留資格を取得しなくてはいけません。いわゆる就労系の資格です。あくまで特別な場合ですが、親、兄弟が病気の場合、医療滞在ビザや、内戦など生命の危険がある場合は、難民申請など、特別在留の可能性もあります。
医療・福祉について
病気をしたら…高額療養費制度
病院にかかるお金は3割負担とは言え、入院ともなると3割でも大きな負担になります。そこで、療養に係る高額の医療費が生じた場合、所得にしたがって負担を軽減する「高額療養費」の制度があります。
これは、被保険者またはその被扶養者の負担すべき医療費が所得ごとに規定された基準(自己負担限度額)以上になった場合、その超えた額を「高額療養費」として支給する制度です。
70歳未満の場合、所得の区分が 5つに区分され、それぞれ基準額を超える医療費負担分が高額療養費として支給されます。ただし、この高額療養費は、被保険者またはその被扶養者が「同一の月」にそれぞれ「同一の病院等」から受けた療養に係る医療費の合算額で計算します。つまり、月をまたいでの医療費は、同一の病気でも別に計算します。
高額療養費の対象となる医療費は、「同一の月」かつ「同一の病院等」から受けた療養を合算します。「同一の病院等」とは、同じ病院であっても「医科と歯科」、「通院と入院」は別々に取り扱います。また、原則として「同一人」の医療費を対象としますが、世帯合算の制度もあります。被保険者・被扶養者の医療費負担分が、それぞれ単独では高額療養費の支給要件を満たさない場合であっても、同一の世帯で同一の月における医療費の負担分の額がそれぞれ21,000円以上であるときは、それぞ
れの額を合算して計算することができます(なお、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近1カ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
高額療養費は、原則的には現金給付(事後給付)ですが、あらかじめ保険者(健康保険の場合は全国健康保険協会もしくは健康保険組合、国民健康保険の場合は市町村および特別区もしくは国民健康保険組合)に申請して「限度額適用認定証」を受けた場合は、病院で先に医療費負担分を支払う必要がありません。
生活保護と外国人の状況
◇生活保護受給者は増加傾向にあると言われてきましたが、景気の回復?の影響で一 昨年に比べて減少をしているそうです。
昨年末時点で、生活保護を受給している人は約212万人、世帯数としては164万世帯 です。
この212万人の生活保護受給者のうち、高齢者が53%を占めており、この高齢者の うち、91%が単身の高齢者となっています。
その次に障害のある人や傷病者のいる世帯が25%、母子世帯が6%、そしてその他 世帯が14%を占めています。
全体として生活保護を受給している人の数は減少したようですが、単身の高齢者の 受給者が増加をしています。
◇外国籍の生活保護受給者は約6万9千人で、世帯数としては約4万5千世帯です。上記 の全ての生活保護受給者のうち外国籍の生活保護受給者の占める割合は3.28%、世帯数では2.8%です。この数字からみると、決して、日本人の生活保護を圧迫するような数字ではないことがわかります。
◇外国籍の生活保護受給者の現状を国籍別でみると、一番多いのが、韓国・朝鮮籍、 次いで中国、3番目にフィリピン、4番目にブラジル・ペルーとなっています。
外国籍の受給者の中では、在日同胞が一番多いのですが、そのうち65歳以上の高齢 者世帯が6割を占めており、その高齢者世帯のうち単身世帯は8割を占めています。これには長らく年金制度から排除され、無年金のままに放置されている同胞高齢者の実態がそのまま反映されています。ちなみに日本人の生活保護受給者の平均年齢は56歳だそうですが、同胞受給者の平均年齢は61.7歳です。
◇2番目に多い中国国籍の受給者の場合、単身の傷病世帯が多くを占めており、3番目 のフィリピン国籍の受給者の場合は、子のいる母子世帯が多く、4番目のブラジル・ペルーの受給者の場合は、単身の稼働年齢世代の世帯が多くを占めているとのことです。
外国籍の生活保護受給者にはその来日の背景によってその特徴があらわれていると言 えます。
新型コロナウィルス関連 各種生活支援制度
生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウィルス感染症が日々の暮らしに深刻な影響をもたらしている中、各種の生活支援のための事業が実施されています。
ここでは、社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度について解説します。
◆生活福祉資金貸付制度とは?
全国の都道府県の社会福祉協議会が実施している貸付制度です。
低所得、障害のある人や65歳以上の高齢者のいる世帯を対象に、無利子または低利で、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金を貸し付けています。具体的には、就職に必要な知識・技術等の習得や高校・大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等、教育支援資金・福祉資金等の他、緊急小口資金の貸付があります。 また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。
★昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大を踏まえ、収入が激減した世帯の生活福祉資金の中のとりわけ、①緊急小口資金と②総合支援資金については、保証人がいなくても、無利子で借りることができる、据え置き期間、償還期間の拡大等の特例の措置が設けられています。
① 緊急小口資金
新型コロナウィルス感染症の影響により、休業などにより収入が減少したため、緊急かつ一時的に生活維持のための資金が必要になった世帯が対象です。
貸付の金額は10万円以内(一律10万円ではありません。対象者の状況により10万円以内の必要な金額となります。)です。ただし、世帯の中に、小学校等の休業等で子の世話をする必要のある人、要介護の人、新型コロナウィルスに感染した患者がいたり、あるいは世帯員の数が4名以上の世帯などは20万円以内まで貸し付けが可能です。
厚生労働省は、緊急の事態に即応できるよう迅速な処理を求めていますが、申請が受理されてから決定まで、審査には10日間前後かかります。
返済の据え置き期間は貸し付けの日から1年以内で、その期間の経過後2年以内に返済しなければなりません
②総合支援資金
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難で生活の再建が必要になった世帯が対象です。
貸付の金額は、単身世帯の場合は月額15万円以内、家族や同居する人がいる複数世帯の場合は月額20万円以内で、貸し付けの期間は3か月です。
返済の据え置き期間は貸し付けの日から1年以内で、その期間の経過後10年以内に返済しなければなりません。
また、①の緊急小口貸付とは異なり、生活困窮者自立支援法に依拠した自立に向けた継続的な支援を受ける必要があります。
*①,②のいずれも世帯単位での申請になります。
*①,②いづれも、相談者が学生(単身世帯)であっても、新型コロナウィルスの影響に収入の減少等により生活維持が困難であれば、貸し付けの対象になります。
*①、②のいずれも申請窓口は市町村の社会福祉協議会です。
申請に必要な書類は、身分証明書(運転免許証、特別永住者証明書や在留カード等)、印鑑、世帯全員の住民票、新型コロナウィルスの影響による収入の減少の状況がわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳の履歴、勤務表やシフト表など)等です。
*今回の特例措置においては、返済時点においてなお所得の減少が続く非課税世帯については返済を免除する扱いになっています。
*①、②いづれも国籍条項はなく、外国籍者も対象になります。厚生労働省社会・援護局地域福祉課の4月16日付の事務連絡では、国籍にかかわらず対象になるとしているものの、
「貸し付けについては・・・・・資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で決定…・」とあることから、中長期在留者で在留期間が1年未満の人は実際の利用はなかなk困難と思われます。
病気で休職したら…傷病手当金
在職期間中に病気などで就労ができない場合は、健康保険(勤務先の健保組合や協会けんぽ)より傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は会社を休んだ日が連続して3日以上あり、4日目以降の休んだ日に対して支給され、1日につき、標準報酬額の3分の2に相当する金額が、最長1年6カ月支給されます。現在在職中の休業が対象になるので、退職してから治療をしようとしても傷病手当金は支給されません。健康保険の任意継続期間中であっても支給対象とはなりません。
ただし、在職中にすでに受給要件を満たしている場合は、引き続き受給できます。
精神科等に通院するとき…精神通院医療制度
精神疾患により、通院治療を続ける必要がある人を対象に、医療費の自己負担を軽減するものです。通院時の医療費の自己負担額が 1割となり、また前年度の収入や本人の障害などの状態などにより、月額の自己負担額の上限(例えば、1カ月0円あるいは 10,000円などのように)が決められます。
対象となる疾患は、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの依存症、てんかん、などです。軽減の対象となる医療は、指定された医療機関による精神疾患などでの外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などです。申請の手続きは、市区町村役場の障害福祉課あるいは保健福祉課などです。
家賃を払えない…住宅確保給付金制度
失業などで住まいを喪失あるいはその恐れがある人を対象に、一定期間、家賃相当額を給付し、住まいの確保と就労を支援する制度です。
支給の対象は、①離職後2年以内で65歳未満の人、②離職前に主たる生計維持者であった人 ③就労意欲があり、ハローワークに求職申込みを行っている人、④申請人の世帯収入、預貯金の合計が所定の基準額以下である人、⑤その他、申請人と生計を一にする同居親族が、雇用施策による給付や、自治体などが実施する類似の給付や貸付を受けていないこと、などの複数の要件を満たす人です。
給付金は、申請人にではなく家主または不動産店に直接支払われ、給付期間中は、ハローワークで職業相談を受けたり、週1回以上、求人先に応募または面接を受けるなど、就職活動を行わなければなりません。
生活に困ったら…生活保護
生活保護は、生活に困窮している人に対して、最低限度の生活を保障しようという制度です。申請には、資産の活用・能力の活用・その他の制度活用などの要件を満たす必要があります。自分の預貯金や生命保険、土地・家などの不動産、車などの財産を処分し、さらにあらゆる努力をしてもなお生活が困窮する時に利用ができるというものです。同胞も申請はできます。また外国籍でも「定住者」や「日本人あるいは永住者の配偶者等」の在留資格であれば申請ができます。
生活保護には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助など8種類の扶助があり、その人または世帯の困窮程度に応じて必要な保護がお金や現物で支給されます。困窮に陥った理由や借金の内容などは問われません。なので、借金があっても生活保護の申請はできます。福祉事務所では、申請の時点で借金があると「では、申請は無理ですね」と断られることがありますが、「保護が決まってから法律家を通して借金の整理をします」との旨をきちんと伝えてください。
[ワンポイント] 海外渡航と生活保護
生活保護を受給中だからと言って、海外渡航が禁止されているわけではありません。「帰国」ではなく、一時的に海外へ渡航した場合であって、引き続き日本国内に居住の場所を有している場合、海外に出かけたという事実のみを持って生活保護を廃止することはできません。
次の①~③の目的で、概ね2週間以内の期間で海外渡航をする場合には、保護費をやり繰りして貯めたお金や、あるいは親族などの他からの援助で費用を賄って渡航する場合には、(渡航に係る費用全額を収入認定せずに)その渡航を認めています。
①親族の冠婚葬祭、危篤の場合および墓参
②修学旅行
③公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加(選抜又は招待された場合に限る)
ただし、事前に福祉事務所の担当者には渡航の目的、日程などを伝えてください。上記3つの目的以外で海外に渡航する場合、例えば観光、通常の親族訪問、一時的な里帰りなどの場合は、渡航に係る費用は「収入があったもの」とみなされ、後で保護費の減額や返還を求められることがありますので、注意が必要です。
[ワンポイント] 住宅ローンと生活保護
生活保護は最低限の生活を保障するためのものであり、ローン付きであっても持ち家は資産とみなされるので、原則、処分をする必要があります。ただし、例外があります。
1つは、住宅ローンがあっても、その返済期間が残り5年以内で、残っているローンの総額が300万円以下で、月々の返済額が生活扶助の基準額の15%以下である場合です。すなわち、返済額が少なく、あと一息でローンが完済するような場合です。
2つは、すでに持ち家を売却する予定で、残るローンなどの負債につき破産の手続きを弁護士に依頼しており、ローン返済を停止している場合です。すなわち持ち家を手放すことにした場合です。
退職後の健康保険ー任意継続か国保に加入か?
- この夏から体調がすぐれず、現在休職しながら通院治療中です。回復の目途が立たないので、長年勤めた
会社を退職する予定です。これまで加入していた職場の健康保険を任意継続にするか、それとも国民健康保険
に加入するか、どちらがよいのでしょうか? -
退職後は、配偶者や子などの家族の被扶養者になれない場合、それまで加入していた職場の健康保険の任意継続にするか、または国民健康保険に加入するか、選択しなければなりません。どちらがよいかは、まずは、それぞれの保険料を担当窓口で調べてもらい保険料の額を比べてみるのがよいです。
任意継続の場合、保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担となります。扶養家族がいれば、引き続き扶養に入れることができます。退職後20日以内に手続きを行い、任意継続ができる期間は2年です。
他方、国民健康保険の場合、保険料は前年の収入に応じて算定されるので、退職直後は高めになります。
さらに国民健康保険には扶養という考え方がなく、家族の分まで保険料がかかります。そのため任意継続の場合よりも保険料の金額が高くなることもあります。
解雇・雇止めや倒産、病気などで失職・退職した場合は、保険料を軽減する措置があります。
相談者が傷病手当金を受給中で、退職後に国民健康保険に加入するような場合、相談者が(退職前に)職場の健康保険に1年以上加入期間があれば、退職後も残りの日数分は傷病手当金を受給することができます。
朝鮮学校の就学と生活保護
生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、介護扶助、生業扶助、葬祭扶助など8種類の扶助があります。生活保護受給世帯の状況に応じて、その都度、必要な扶助が加算されて保護費が支給されます。
生活保護世帯に義務教育、すなわち小学校・中学校の学齢期のこどもがいる場合、学級費・教材費・給食費・通学費などが「教育扶助」として支給されます。
朝鮮学校は学校教育法で規定する「学校」ではないことから、「教育扶助」の対象になりません。なので、生活保護を受けている同胞が子を初級部や中級部に通わせている場合、学級費や教材費など一切の扶助を受けることはできません。ところが、朝鮮高校の場合は、「生業扶助」の対象になり、「高等学校等修学費」として保護費に加算されます。
これは、高校進学率の高まりという社会的背景、そして貧困の再生産の防止という観点から、高校等への進学が子どもの自立・就労に有効であるとの判断により、2005年度から「生業扶助」の範囲で新たに「高等学校等修学費」が設けられるようになりました。
この「高等学校等修学費」の対象には、一定の基準を満たす高等学校等に準ずる外国人学校も含まれ、朝鮮高校も含まれています。
子が初級部・中級部に在学中は修学にかかる費用は一切、扶助の対象にはなりませんが、子が高級部に進学すると、「高等学校就学費」として扶助の対象になり、生活保護費に学用品費、学級費や教材費、通学定期代など、入学時には入学準備金等が加算されることになります。扶助の範囲の詳細は、センターまでお問い合わせください。
福祉事務所の担当者が朝鮮高校が扶助の対象になることを知らず、保護費に加算をしていないこともあるので、注意が必要です。
税金が払えない!
住民税や国民健康保険税が払えないとどうなるでしょうか?
納付期限を超えると、まずは督促状が送付されてきます。それでも払わないままに放置していると差押通知書などが送付されます。これらの通知書が手元に届くまでの日数は各自治体ごとに異なりますが、地方税法329条では「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と定めているので、20日以内に送られてきます。
督促状が届いても無視していると、役所の担当者から催促の電話がかかってきたり、自宅を訪ねてくることもあります。それでも納付しない場合は「差押通告書」が届けられ、差押処分となります。法律上では、督促状を発した日から10日以内に納付をしないときは差し押さえができることになっているため、いきなり、預金口座や生命保険、給料などが差し押さえられるということもあり得ます。差し押さえられる場合、滞納処分費や延滞金(1カ月目は2.9%、2カ月目以降は9.2%)もついて本来の金額よりも高くなります。
また、国民健康保険税を滞納し続けると、医療費が全額自己負担となってしまい、病院を受診するたびに高額な医療費を請求されることになります。
失業したり、病気やケガなどのために収入が激減した、無くなったなど、やむを得ない事情がある人には、「分納」「減免」「猶予」などといった措置が取られることがありますので、放置しないで早めに役所に相談することが重要です。
高齢者・介護について
突然の入院
ある日突然、親が入院した。そんな時に混乱せず必要な物(情報)を持って病院へ駆けつける準備はできていますか?同居、別居、遠距離と置かれた状況は様々ですが、最低限の準備をしておけば安心です。まずは入院に際して必要な物(情報)をリストアップしてみましょう。
急性期/一般病院の入院期間は長くて1カ月。できるだけ速やかな退院を求められます。退院後は本人の希望に沿いつつ、病状や家庭状況に応じて回復期リハビリテーション病院などへの転院か、自宅・福祉施設などでの生活かを決めることになります。また、中長期的に考えると、入院中に介護保険の申請も検討が必要です。
入院費用と事前にできる対策
①限度額適用認定証
手術などで高額な医療費がかかることが事前に分かっている場合は、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の申請をしましょう。医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなり、窓口での支払いを抑えることができますし、払い戻し手続きの手間も省けます。認定証は各健康保険(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、後期高齢者医療など)に申請し発行してもらいます。
②入院保証金
病院によっては「入院保証金」を預かることがあります。金額は 5~10万円程度が相場で、自動車事故は2倍になるケースが多いでしょう。預り金なので退院時に返金(入院費の精算)されます。
*病院には MSW(医療ソーシャルワーカー)を配置しているところがあります。医療費や退院の相談、さらには介護保険などの相談にものってくれます。困りごとがあれば気軽に相談してみましょう。
生命保険と指定代理請求制度
生命保険と指定代理請求制度入院した親が生命保険に加入していて、本人が保険金・給付金の請求を行えない場合、家族・親族などが代理で請求を行えるサービスです。通常は契約時に指定しますが、途中からの変更・付加も可能です。代理人の範囲や手続きは保険会社によって異なります。また、入院が長期にわたる場合は、退院前に保険金・給付金を請求できるサービスもありますので、事前に保険会社に確認してみましょう。
介護保険を利用するには…
介護の始まりは突然です。病気、骨折、認知症、原因は様々ですが、初めてのことに戸惑いながらも次々と事務手続きを済ませ、ことを前に進めなければなりません。これらはほとんど平日昼間に時間を取らねばならず、会社や仕事の都合をつけるだけでも一苦労。親と離れて暮らす遠距離介護の場合はさらに大変でしょう。
こうした事態に備えて、介護の始まりに必要な知識を時系列で整理し頭に入れておきましょう。やるべきことの量は変わりませんが、全体像が見えているだけで、混乱やイライラを減らすことができます。
最初の相談は「地域包括支援センター」へ
親に介護が必要だなと感じたら、まずは親の居住地の「地域包括支援センター」に相談しましょう。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった専門家が配置されているので、介護制度に関する一般的なアドバイスだけでなく、医療・福祉・保険などの制度を網羅した総合的な相談、支援が可能だからです。
老人福祉施設に併設されていることも多いので、土日の相談が可能な場合も多く、相談は無料でできます。役所のホームページや広報などで住所地所轄のセンターを調べることができます。また、お近くの「居宅介護支援事業所」も地域包括支援センター同様に認定申請の手続きや介護相談に対応してくれます。
介護保険の申請と要介護認定
介護保険は、①要介護認定申請②訪問調査(ご自宅又は入院入所施設において)③要介護認定審査、という手順をふむことで利用することができます。訪問調査では、行政から委託された調査員が心身の状態や生活環境をチェックします。できれば普段の様子を把握している家族が立ち合い、本人の現状を正確に伝えましょう。調査の後は、どの程度の介護(支援)が必要かを判定する要介護認定が行われ「要介護度区分」が決定します。ここまでに申請日からおよそ1カ月かかるとされていますが、早急にサービスの利用が必要な場合は、認定前でも暫定的にサービスを利用できる場合もあるのでケアマネジャーに相談してみましょう。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス(自宅で生活する方が対象)と施設サービス(入所)、地域密着型サービスなどがあり、要介護(支援)度によって利用できるサービスが異なります。
通常、居宅介護支援事業者(要介護)または地域包括支援センター(要支援)に依頼し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成しますが、利用したい施設やサービス、自宅介護での困りごとなどを積極的に相談し、それぞれの家庭にあった介護サービス計画を立てましょう。
同胞のいる介護施設を探す
デイサービスの利用や施設への入所を考える時、普段の食生活や風習、言葉の問題などから、同胞の利用者や職員のいる施設を探すこともあるでしょう。地域によっては同胞が経営する介護施設や、同胞が多く通うデイサービス、特別養護老人ホームなどがあります。詳細は当センターへお問い合わせください。
無年金者と介護保険
同胞に多い無年金の高齢者で無職の場合、介護保険料の支払いは経済的に大変です。また、年金からの特別徴収が出来ず納付書による支払いとなるため、払い忘れや滞納も生じやすくなります。介護保険料の未納・滞納が続くと、「償還払い」や「保険給付の一時差し止め」、「利用料3割負担」などのペナルティーを受けることになります。こうした事態に陥る前に、一定要件のもと減免を受けられる場合もあるので、早目に市区町村の担当窓口に相談しましょう。
[ワンポイント] 要介護(支援)認定と扶養控除
要介護(支援)認定を受けている場合、身体障害者手帳などを持っていなくても、市区町村役場で「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえば、所得税・住民税の障害者控除、または特別障害者控除を受けられます。
居住地の介護保険認定担当窓口に申請し、「認定書」が発行されたら年末調整や確定申告時に添付書類として提出して下さい。場合によっては最高 5年までさかのぼって税金の還付を受けることができる場合があります。ただし、市区町村によって発行条件が異なるので、事前に詳細を確認しましょう。
[ワンポイント] 成年後見制度
認知症などによって判断能力が十分でない人々を法律・生活面で支援する制度です。具体的には、認知症や知的障害、精神障害などにより、日常的に判断能力を欠くため、不動産や預貯金などの財産や日常生活における金銭管理が十分にできない、あるいは病気で入院をする際の諸手続きや、介護が必要になった際の施設への入所手続きなどを適切に行うことができず、不利益を被ることが無いよう、本人の自己決定権を尊重しつつ、その人に代わって権利を擁護しようというものです。
大きくは法定後見人制度と任意後見人制度の 2つがあり、すでに認知症の診断を受けている人の場合は、その判断能力の程度に応じて、補助人、補佐人、成年後見人のいずれかを家庭裁判所で選任してもらいます(医師による所定の診断書が必要です)。
後見人の選任を申し立てることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長他などです。身寄りや親族がいない場合は、担当のケアマネジャーや市区町村役場の高齢者福祉課の担当者と相談するのがよいでしょう。
後見人には、子などをはじめ親族や、親族以外では弁護士や司法書士、社会福祉士などの法律や福祉の専門家その他の第3者や福祉関係の法人などが選任されることがあります。
認知症になったら
認知症の始まりの時期は、家族も対応に戸惑いがちですが、正しい知識をもち適切な対応を行うことで、本人も家族も落ち着いた日常生活を送ることが可能です。
認知症の種類と症状
認知症とは、脳の認知機能が障害されたことにより、生活に支障が出ている状態をいいます。そして、ひと言で「認知症」と言っても、その種類や症状は様々です。
認知症といえばアルツハイマー型が代表的ですが、それ以外にもレビー小体型、脳血管性認知症、前頭側頭葉変性症などがあり、それぞれ特徴が異なります。
認知症によりあらわれる記憶障害や判断力の低下などの中核症状は誰にでも起こる症状ですが、徘徊や物盗られ妄想などの行動・心理症状は性格や環境などが大きく作用するため、人によってその症状は多様です。
早期発見、早期診断は「かかりつけ医」から
加齢によるもの忘れだけではない、「何かおかしいな」と感じることが多くなったら、まずは普段かかっている「かかりつけ医」に相談しましょう。内科や整形外科などの診療科目に関わらず、定期的に診察している医師であれば、患者の変化にも敏感です。認知症が疑われる場合は、専門機関につないでもらえるかもしれません。また、早期発見することで家族が今後の対応をじっくり考える余裕ができ、認知症の種類によっては薬で進行を遅らせることも可能になります。
近年、認知症についてのアドバイスや診断、専門医療機関の紹介などを行う「認知症サポート医」制度も整ってきました。どこの医療機関(病院・診療所)に相談・受診すればよいのか分からない場合は、近くの「認知症サポート医」に相談してみましょう。
[ワンポイント] 認知症サポーター養成講座
「認知症サポーター」は厚生労働省が推進する事業で、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「サポーター」を養成し、認知症になっても安心して暮らせる社会を目指すものです。養成講座は小学生から社会人まで誰でも受講可能で、所要時間は 90分程度、受講料も無料です。全国各地の自治体で開催されていますが、地域の団体には出前講座も可能とのこと。詳しくは自治体の高齢者窓口にお問い合わせください。
認知症サポート医ネットワーク
認知症の発症初期から状況に応じて、医療と介護が一体となった認知症の人への支援体制の構築を図ることを目的に、厚生労働省は2006年から「認知症サポート医養成研修事業」を実施しています。
認知症サポート医は、かかりつけ医の認知症判断などに関するアドバイザー役となり、地域医師会と地域包括支援センターとの連携づくりや、かかりつけ医の認知症対応力向上の研修にも関わっています。
認知症かも知れない、でもかかりつけ医もない。そんな時は下記リンク先から居住地の「認知症サポート医」を探してみましょう。
ひとりで抱え込まないで
認知症と聞くと、徘徊や暴力、物盗られ妄想などの「問題行動」を真っ先に思い浮かべる人が多いようです。そのためか、認知症になると何も分からなくなってしまう、という不安や偏見も根強く残っています。
認知症による記憶障害や判断力の低下から「問題行動」が引き起こされるのは事実ですが、実はこれにも「幼いころ住んでいた家に戻りたい」「子ども扱いする家族や職員が腹立たしい」など、本人なりの理由があると言われています。介護する側がゆったりとした心と敬いの念を持って対応することで、「問題行動」も本人の意思表示へと変わるのです。認知症になっても人間の自尊感情は最後まで残っていることを、常に忘れずにいたいものです。
しかし、頭では分かっていても実際には戸惑いや怒りを抑えられないところに、家族介護の難しさがあると言えます。仕事と介護の両立や、社会からの孤立などにより精神的に追い詰められることも珍しくありません。そうした時はケアマネジャーや家族会に頼って、一人で抱え込まないようにしましょう。
認知症との付き合いはゴールの見えないマラソンのようなものですから、家族が介護の犠牲になるだけでは本人の幸せも守れません。デイサービスやショートステイ、家族会や認知症カフェなどを上手く活用し、本人も家族も、外部とのコミュニケーションが断たれないように工夫することが大切です。
在日同胞 1世の場合、認知症により母国語と日本語の使い分けができなくなったり、対応する職員に知識や理解がなく、コミュニケーションが図れない場合があります。また、1世でなくても同胞コミュニティでの生活が長かった場合などは、日本人だけの施設に通うことに抵抗を感じることもあります。認知症になっても最後までその人らしく過ごせる環境を整えるために、地域の同胞コミュニティが持つ資源を活用することが求められています。
自宅で暮らすために…
介護の必要な状態になっても、住み慣れた家で暮らしたいと思うのは自然なことです。ちょっとした自宅の改修や福祉用具の活用で、そうした思いをかなえ、その人らしい生活を守ることができます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修に係る費用を支給するサービスです。支給限度は要介護状態区分に関わらず一律 20万円 (上限額)、そのうちの1割又は2割は自己負担になります。転居された場合や要介護が軽度より重度になった場合に、再度改修を行うことができる場合もあります。申請先は市区町村役場になりますが、必ず改修前にケアマネジャーに相談するようにしましょう。
<申請>
⦁ 改修前に必ずケアマネジャーに相談する
⦁ 住宅改修費に対する支給限度基準額(20万円)の範囲内でかかった費用の1割(一部2割)が自己負担
⦁ 事前申請かつ、認定有効期間内に行われた改修が支給対象
⦁ 被保険者証に記載されている住所であること
⦁ 介護保険料の未納があると、支給対象とならない場合がある
<種類>
⦁ 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわりなどへの手すりの設置⦁ 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げなど
⦁ 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん・板材など)
⦁ 扉の取替え(開き扉・引き戸・折り戸など、ドアノブ交換など)
⦁ 洋式便座などへの便器の取替え
⦁ 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、壁・柱・床材の変更など)
福祉用具のレンタル
車いすや特殊ベッド、歩行器など 13種目の福祉用具をレンタルできます。本人の状況にあった福祉用具を選ぶ必要があるため、必ず福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談しましょう。利用にあたっては、要介護(支援)度に応じた支給限度額の範囲内で、レンタル料の1割又は2割が自己負担となります。
<種類>
⦁ 車いす
⦁ 車いす付属品
⦁ 特殊寝台(電動ベッド)
⦁特殊寝台付属品
⦁ 床ずれ防止用具
⦁ 体位変換器
⦁ 手すり
⦁ スロープ
⦁ 歩行器
⦁ 歩行補助つえ
⦁ 認知症老人徘徊感知機器
⦁ 移動用リフト
⦁ 自動排泄処理装置
[ワンポイント] 特定福祉用具販売
入浴・排せつ用具のように、レンタルすることに心理的抵抗を感じるものを「特定福祉用具」と言います。これらは、いったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」が原則です。給付金額の上限は年度間(4月~3月)10万円以内です。
<種類>
⦁ 腰掛便座
⦁ 特殊尿器
⦁ 入浴補助用具
⦁ 簡易浴槽
⦁ 移動用リフトのつり具の部分
高齢者の住まい
高齢者の住まいの住み替えは、失業や病気などによる経済状況の悪化、持ち家の老朽化や維持の困難、一人暮らしへの不安、また高齢を理由にした退去要求など、その原因は深刻です。
しかし、高齢の単身世帯や夫婦のみの賃貸住宅への入居は、「入居拒否」という壁にぶつかることが珍しくありません。例えば、保証人の不在、低収入や認知症の発症による家賃の滞納、火災や孤独死の心配など、家主にとってはリスクが高い、という理由からです。
そこで、こうした高齢者の住み替え問題解決のため、公共機関・民間による各種の高齢者向け住宅が整備されており、市区町村役場の高齢者相談窓口などで、資料の入手や相談が可能です。
また、自治体によっては家賃、礼金、転居費用などの初期費用を助成する制度もあります。まずは入居条件や家賃、提供されるサービスなど物件の特徴をしっかり理解し、準備資金や世帯構成、健康状態や将来的な福祉施設などへの入所の可能性なども考慮し、物件を探すことが大切です。
[ワンポイント] 主な高齢者向け住宅の種類
基本的に60歳以上の単身者または高齢者夫婦で、自立した生活を送れる人が入居対象となります(一部、要介護認定を受けた方も入居可能)。
①有料老人ホーム(住宅型)
食事等の生活支援サービスが付く民間施設。
②サービス付き高齢者向け住宅
バリアフリー等の条件を備え専門家による安否確認、生活相談サービスが受けられる民間住宅。
③シルバーハウジング
設備等が高齢者向けに配慮され、生活相談員による相談サービス等を受けられる公的(地方公共団体・UR)な賃貸住宅。
65歳以上の同胞高齢者の男女別人口
法務省の在留外国人統計によると、2017年12月末時点で、在留カードもしくは特別永住者証明書をもって日本に在留する「朝鮮」「韓国」の同胞数は481,522人。そのうち、「朝鮮」の同胞数は30,859人、「韓国」の同胞は450,663人です。
これらの同胞のうち、65歳以上の同胞高齢者は123,569人で、先の全同胞数を踏まえると、高齢率は25.6%となります。日本社会の高齢率と近い数字です。
では、この同胞高齢者を男女別、国籍表示ごとの男女別でみると下記のとおりになります。
| ●65歳以上の「朝鮮」・「韓国」同胞 | 男 | 女 | |
| 65~69歳 | 17,998 | 20,542 | |
| 70~74歳 | 14,277 | 17,267 | |
| 75~79歳 | 9,961 | 14,644 | |
| 80歳以上 | 9,405 | 19,475 | |
| 合 計 | 51,641人 | 71,928人 | 123,569人 |
| ●65歳以上の「朝鮮」同胞 | 男(朝鮮) | 女(朝鮮) | |
| 65~69歳 | 2,092 | 1,623 | |
| 70~74歳 | 1,615 | 1,492 | |
| 75~79歳 | 1,182 | 1,297 | |
| 80歳以上 | 1,177 | 1,815 | |
| 合 計 | 6,066人 | 6,227人 | 12,293人 |
*「朝鮮」表示の同胞数は30,859人なので、これで「朝鮮」表示の同胞の高齢率を計算すると、39.8%となります。
| ●65歳以上の「韓国」同胞 | 男(韓国) | 女(韓国) | |
| 65~69歳 | 15,906 | 18,919 | |
| 70~74歳 | 12,662 | 15,775 | |
| 75~79歳 | 8,779 | 13,347 | |
| 80歳以上 | 8,228 | 17,660 | |
| 合 計 | 45,575 | 65,701 | 111,276 |
*「韓国」表示の同胞数は450,663人なので、これで「韓国」表示の同胞の高齢率を計算すると、24.7%となります。男性よりも女性のほうが長寿であり、同胞社会も超高齢社会であることがわかります。
(法務省HP・在留外国人統計より作成・文責 金静寅)
こんな相談 高齢者の施設入所と世帯の分離
- 2年前、同居する高齢のオモニが自宅で転倒し骨折、入院しました。医師から「今後は在宅での介護は無理」と言われましたが、すぐに入所できる特別養護老人ホームもなく予約待ち状態です。とりあえず介護老人保健施設に入所しましたが、毎月の利用料の支払いがきつく、やりくりが困難です。このままでは私たち家族も生活困窮に陥るので、施設に入所中のオモニだけ生活保護を受給することはできないでしょうか?
-
現在老人保健施設に入所中のオモニと、相談者の世帯を分離して、オモニだけ生活保護の申請ができるのか、という相談ですね。施設入所が長期におよび、また在宅生活の見込みが無い状況であっても、オモニが「老人保健施設」に入所中という場合、世帯分離は困難と思われます。介護老人保健施設は、傷病などで入院していた高齢者が自宅に戻るための機能回復訓練を行う「中間施設」として位置づけられています。これにたいし、特別養護老人ホームは自宅で自力で生活することが困難な状態の人のための「生活施設」で、入所期限がありません。
『生活保護法による保護の実施要領』によると、「居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合」の例として、介護老人保健施設に入所している場合を挙げています。さらに、「世帯分離をして差支えない」例として、特別養護老人ホームを挙げています。
特別養護老人ホームへの入所は予約状況や時間など、容易ではないのが現状ですが、今後、オモニが特別養護老人ホームに入所した場合は世帯分離をして、オモニのみを単身世帯とする生活保護の受給は可能になると思われます。
年金について
老齢年金の仕組み
日本の年金制度は「2階建て」の形になっています。外国籍者を含む20歳以上60歳未満の全住民が国民年金制度の加入対象になっており、自営業者や学生(1号被保険者)、会社員(2号被保険者)、専業主婦(3号被保険者)もすべて「1階部分」にあたる国民年金(基礎年金)への加入が義務付けられています。
その中でも、「厚生年金」に加入している会社で勤めている会社員などは、国民年金に加えて厚生年金に加入することとなり、将来の老齢年金も、原則65歳から受給できる老齢基礎年金に加え、「2階部分」の老齢厚生年金を受給できます。
老齢年金を受け取るために最低限必要な年金加入期間(受給資格期間)は、2017年
7月までは25年(300カ月)でしたが、2017年8月から10年(120カ月)に短縮されました。
たとえば、厚生年金加入記録が15年しかなく、年金受給開始年齢であるにも関わらず年金を受給していなかった方も、2017年9月分から年金を受給できるようになります。
なお、受給資格期間は、原則的に①保険料納付済期間、②保険料免除期間をあわせて計算します。これで受給資格期間を満たせない場合は、③合算対象期間(カラ期間)を合わせて計算できます。③のカラ期間は、国籍要件で制度上年金に加入できなかった期間(1961年4月~1981年12月の間で本人が 20歳~60歳の期間)などがあります。
なお、場合によっては本人の職歴が年金記録に正確に反映されていないこともあります。年金記録を照会し、年金が増額した方や新たに年金を受給できるようになった方もいますので、一度しっかりと年金記録を確認することをおすすめします。
在日同胞の無年金問題とは
国民年金制度が始まったのは1961年4月です。当時は国籍条項があり、長らく在日同胞は国民年金に加入することはできませんでした。
日本政府は1979年に国際人権規約を、続く1981年に難民条約を批准しました。その結果、日本の社会保障制度における国籍条項が撤廃されることになり、在日同胞もようやく国民年金に加入できるようになりました(1981年1月1日から)。
(*国籍条項により在日同胞が国民年金に加入できなかった1961年4月~1981年12月末までの20年9ヶ月は後に「合算対象期間」(カラ期間)として年金受給資格期間に算入できるようになりました。*)
しかし、その時点で①すでに60歳を超えている人と②20歳を超えている障害のある人については、何らの救済措置も講じられないままに年金制度の対象から除外されてしまいました。さらに、その時点で③35歳以上の人も同様に年金制度から除外されたのです。
何故、35歳以上の人が除外されたのか。年金に加入できるのは60歳までで、年金が受給できるためには25年の保険料納付期間が必要だったため、1982年1月1日時点で35歳以上の同胞は、保険料を納付しても60歳までに25年の納付期間を満たすことができず、国民年金に加入して保険料を納付したところでそれが「掛け捨て」になってしまうという問題が生じたからです。
1986年の国民年金法のさらなる改正により「カラ期間」制度が導入されました。それにより25年の納付期間が満たせない人が救済される仕組みができたことで、上述③の35歳以上の同胞にも年金受給の途が開かれることになりました。しかしながら、この1986年の改正時点ですでに60歳を超えている同胞はこのカラ期間を用いても納付期間を満たせず、年金制度から除外されてしまったのです。
国民年金制度が発足して以降、無年金になった日本人(例えば、沖縄、小笠原返還時、中国残留帰国者)にたいしては、それぞれ救済のための福祉年金などの経過措置が講じられたにもかかわらず、上述の在日同胞らにはなんらの救済措置も講じられないまま放置されたままです。同胞の無年金問題にはこのような経緯があります。
受給資格期間の短縮とカラ期間
2017年8月に施行された「改正年金機能強化法」により、老齢年金の受給資格期間が25年(300か月)から10年(120か月)に短縮されています。すでに10月(9月分)から支給がスタートしています。
注意すべきは、10年短縮により新たに受給対象となった人には「年金請求書」が日本年金機構より郵送されましたが、「カラ期間」を用いて10年を満たす人の場合は「年金請求書」が送付されていません(一般的な制度改正の案内のみが郵送されているようです)。したがって、しっかりと自分自身で適カラ期間をチェックしなければ、受給資格があることに気が付かず、年金をもらいそびれることにもなってしまいます。
「カラ期間」の計算については、在日本朝鮮人人権協会が発行したリーフレット「同胞のための年金Q&A」もしくはチラシ「あきらめていたあなたも年金がもらえるかも!?」をご参照ください(同胞高齢者の大多数が「カラ期間」があります)。
年金の請求には、①年金請求書(最寄りの年金事務所でもらうことができます)、②本人の住民票(世帯全体のもの。年金請求を目的とする場合、無料になる自治体があります)、③特別永住者証明書(もしくは在留カード)が必要です。なお、請求手続きは代理でも可能です。特に資格は必要ありませんが、④委任状(「年金請求書」の中に委任状のフォーマットが入っています)、⑤代理人の本人確認書類(免許証・特別永住者証明書等)、⑥請求者本人の特別永住者証明書(もしくは在留カード)の両面コピーが必要になります。
年金の請求手続きの窓口は、各地域の年金事務所です(年金加入記録がすべて国民年金第1号被保険者の方は市区町村役場の年金担当窓口でも可能です)。
同胞ならではの年金相談事例
事例1
Aさんは、1945年1月3日生まれの特別永住者の女性。これまで年金保険料を納めた記憶もなく、自営業者の夫も年金保険料を払った記憶がないので、年金を諦めていました。
Aさんは総聯支部の会合で、受給資格期間の短縮と「カラ期間」の説明をうけ、自身の対象カラ期間が17年(204か月)あることがわかりました。カラ期間だけで10年以上あるので、あと1か月でも保険料納付済期間、もしくは保険料免除期間があれば、新たに年金を受給できるということです。
Aさんは自身の職歴を振り返り、30代のときにパートで数か月働いていたことを思い出しました。しかし40年ほど前のことなので、会社名も場所も曖昧な記憶しかありません。それでも、会社のあったおおよその場所(東京都中央区あたり・・・など)や業種(繊維業、ゴム工場など)といった情報をできる限りあげると、年金事務所がそれをもとに調査してくれるときいたので、Aさんの息子のBさんが代理で年金事務所に行き年金記録を照会したところ(本人の「委任状」があればだれでもできます)、パートの5か月の厚生年金加入記録がみつかったのです。使っている名前が変わっていたこと、住所変更をしていなかったことなどで、年金記録が宙に浮いていたのです。年金機構によれば、現在2200万件の記録が宙に浮いた状況で、年金記録を照会した9人に1人は年金記録がみつかっているとのことです。
――これでAさんは204か月のカラ期間と5か月の保険料納付済期間により、改正年金機能強化法による制度改正後の受給資格期間(10年=120か月)を満たし、保険料5か月分なので少額ですが、今年10月から新たに老齢年金(9月分から)を受給できるようになります。
このように在日同胞の場合、職場で日本名や民族名など違う名前をつかっていたりするので、年金記録が本人と繋がっていない可能性が高く、そういった年金記録を掘り起こすことで、年金が増額したケースや新たに年金を受給できるようになったケースが数多くあります。同胞ならではの重要なポイントです。
かりにAさんが既に保有している自身の年金加入記録に、カラ期間をあわせると25年以上あることが分かった場合、現行法で既に受給資格を満たしているので、9月分からではなく、もらいそびれている年金(5年の時効で消滅していない分)を含めてすぐに年金を受給することができます。なお、記録照会などにより年金記録が訂正されて25年の受給資格期間を満たした場合の年金(もしくはすでに年金受給している方の年金記録訂正による増額分)は、年金時効特例により時効消滅分(5年以上前の年金)も含めてすべて受給できるので、高額の年金を取り戻すケースも想定されます(遅延特別加算金も加算されます)。
事例2
Qさんは1928年3月生まれの在日2世で、89歳になりました。
Qさんが66歳の時、夫が死亡したので、その時から現在まで会社員だった夫の遺族年金を受給してきました。Qさんはずっと専業主婦で、内職の経験はあるものの、勤めた経験は一切ありません。
ところが、息子がたまたまQさんの閉鎖された外国人登録原票を取り寄せたところ、Qさんの勤務先欄に大阪のカバン加工会社の名前が記入されていました。
そこで、息子が時間をかけてQさんに聴き取りをしたところ、戦後間もない頃、大阪のカバンをつくる工場でちょっとアルバイトをしていたと言うのです。その記憶をもとに年金事務所で(Qさんの本名、結婚前の通称名、結婚後の通称名、新暦・旧暦の生年月日などをもとに)Qさんの年金加入記録を調査したところ、なんと24か月の厚生年金加入期間が見つかったのです。
Qさんには永住外国人のカラ期間と会社員の妻のカラ期間を合わせ24年あります。また、1930年4月1日以前の生まれの人には、生年月日による受給資格期間の短縮特例があります。1928年3月生まれのQさんの場合、受給資格期間は22年です。Qさんはこの特例を満たすことになり、見つかった24カ月の厚生年金加入期間について老齢年金の受給資格があることがわかりました。
Qさんは66歳から夫の遺族年金を受給しているので、66歳以降現在までのQさんの老齢年金については受給権が停止となりますが、60歳から66歳までの6年間分が「もらいそびれ」ということで請求が可能となりました。
Qさんの場合、実際に加入した期間は24か月なので、年額8万7千円の老齢年金(基礎年金部分+報酬比例部分)がもらえることが判明しました。
年金記録が訂正されたことから「時効特例」の対象となり、60歳から66歳までの6年分(約50万円)が遡って支給されることになりました。
事例3
昨年の1月、Bさんのアボジが90歳で亡くなりました。葬儀も終わり、Bさんが高齢のオモニに代わって年金事務所で遺族年金の申請をしようとしたところ、韓国の家族関係登録簿にあるアボジの生年月日(1926年3月9日)と死亡届けに記載されている生年月日(1926年6月10日)が異なることを指摘されました。Bさんはその時はじめて、アボジが生前に韓国の法院で生年月日の訂正をしていたことを知り、死亡届けにある生年月日を家族関係登録簿の記載に合わせて訂正(追完による訂正)をしました。
ところが、数日後に年金事務所から連絡があり「アボジの生年月日が1926年3月10日なので、アボジは年金受給資格期間を満たしておらず、そのため、本当は老齢年金の受給資格が無いのに年金をもらっていたことになる。亡くなるまでの過去5年間に遡って5年間分の年金(約350万円ほど)を返還してください」と言われたのです。
何故、そんなことになったのでしょうか?
在日同胞には長らく年金制度から排除されていた時期があります(1961年4月~1981年末)。その後の1986年の制度改正により、その期間を「カラ期間」として年金受給資格期間に算入することができるようになったものの、1926年4月1日以前の生まれの人はこの「カラ期間」は適用されません。
Bさんが承知していたアボジの生年月日は1926年6月10日です(アボジの特別永住者証明書上の生年月日も同じ)。アボジのカラ期間は20年9か月あります。アボジがかつて製薬会社に勤めていた時に加入していた厚生年金の7年間を足して27年9か月となるので、アボジは少額ではあるものの老齢年金を受給できていたのです。
ところが、生年月日が1926年3月10日となると、「カラ期間」の適用が無いためこの20年9か月が無くなり、25年の受給資格期間を満たしません。なのでアボジには受給資格が無かったのに、年金をもらっていたということになるのです。
これまでアボジが受け取った年金分を返せと言われても、5年分なので莫大な金額です。途方にくれたBさんがセンターを訪ねてきました。
センターでは詳細を伺い、Bさんからアボジの生活史を聞いてみたところ、戦前に来日したアボジは、解放後、何度も仕事を変えていたとのことでした。そこで、ダメ元で、アボジの外国人登録原票を取り寄せ、そこに幾つか勤務先が書いてあったことから、センターの専門相談員をとおして年金事務所であらためてアボジの年金加入記録を調査したのです。調査にはかなりの時間がかかりましたが、なんと25年を上回る加入記録が出てきたのです。あらたに年金記録が見つかったことから、アボジの年金加入記録が訂正され、合わせて年金の金額も訂正されました。その結果、アボジが生前にもらいそこねていた年金額が65歳から無くなる90歳までの25年分(時効特例)が一括して支払われることになったのです。*Bさん「宝くじにあたったようなもの!」と大喜び♥♥
かつて「宙に浮いた年金記録問題」が世間を騒がせた時期がありましたが、在日同胞の場合、様々な要因・背景から、年金記録は「宙に浮いた」り、バラバラになっていることが多く、Bさんのようにあっと驚く事例が他にもあると思われます。是非、アボジ・オモニの年金記録もダメ元でも調査してみることをおすすめします。
カラ期間って?
1961年4月、「国民皆年金」をうたって施行された国民年金。在日同胞をはじめ外国籍の人は、不当にも国籍要件があったため、国民年金制度から排除されていました。また、日本国籍者でも会社員の妻や学生は、年金加入が任意とされていました。
1982年に国籍要件が撤廃され、現在では強制加入となったことから、このようにかつて制度的に排除されていた期間や任意加入だった期間は、年金額には反映されないものの、年金を受け取るため受給資格期間に算入できる機関として扱われます。この期間を「合算対象期間(カラ期間)」と言います。
在日同胞の場合、カラ期間は・・・・
本人が20歳から60歳未満の期間で
①特別永住者/永住者の1961年4月~1981年12月末の期間
②厚生年金/旧共済年金加入者の配偶者の1961年4月~986年3月末の期間
③日本の大学・短大等の学生であった1982年1月~1991年3月末の期間
*日本国籍の場合は、1961年4月~1991年3月末の期間
1世、2世の同胞の場合、①のカラ期間がある方が多いので、要チェックです。とりわけ、カラ期間を合算することにより10年以上になる方の場合、年金請求書は送付されませんので、特段の注意が必要です。自分はもちろん、アボジ・オモニのカラ期間も調べてみることをおすすめします。
障害年金・遺族年金
けが・病気などで障害を負ったり、稼ぎ手が亡くなり生活が困難となったとき、障害年金・遺族年金は大きな役割を果たします。「若いから大丈夫」と、年金保険料を納めないままにしていると、万一の時に障害年金・遺族年金が受給できなくなる可能性があります。
障害年金と遺族年金の受給要件は似ています。障害の原因となったけが・病気について、初めて病院で診療を受けた日(初診日)、または死亡日の前日において、①保険料納付済期間と②保険料免除期間を合わせた期間が、それまでの年金加入期間のうち3分の2以上ある方(もしくは、直近過去1年のうち保険料未納期間がない方)であれば障害年金・遺族年金の保険料納付要件は大丈夫です。
その上で、障害年金は、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、もしくはそれ以前に治癒した場合は治癒した日)に障害等級に該当すれば、障害等級に応じた障害年金が支給されます。障害等級は、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~ 3級まであります。
国民年金の遺族基礎年金は子(18歳未満)のある配偶者か子(18歳未満)が受給でき、遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者と子(第1順位)・父母(第2順位)・孫(第3順位)・祖父母(第4順位)が受給できます(先順位の遺族のみ)。
年金保険料の支払いが困難になったら
20歳になったら国民年金に加入し、年金保険料を納付しなければなりません(*厚生年金などに加入している人、またはその配偶者に扶養されている人は除く)。国民年金の 1カ月当たりの保険料は 16,490円 /月(2017年現在)で、様々な事情で支払いが負担になることもあります。未納・滞納を避けるために下記のような制度があります。
保険料免除制度
所得の少ない人が対象です。本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が一定額以下の場合、申請ができます。所得に応じて、保険料の全額、4分の 3、半額、4分の 1が免除されます。免除の期間・免除の額に応じて年金額が計算され、全額免除の場合でも保険料を全額支払った場合の2分の 1が支給されます。*失業した人や、夫のDVで家を出た妻などは、特例免除があります。
納付猶予制度
本人と配偶者の前年度の所得のみを基準に納付を猶予するものです。50歳未満の人が対象です。納付猶予の場合、免除制度とは異なり、猶予された期間は年金額には反映されません。学生の場合は「学生納付特例制度」のみ利用可能です。
上記の免除・納付猶予の制度には、将来の受給額を増やすため、免除・猶予された保険料を後に10年まで遡って納付することができる追納制度があります。
遺族基礎年金と寡婦年金
- 夫(50歳)が亡くなりました。家族は私とすでに独立した長女、長男(大学3年)、次男(中学1年)です。自営業で夫婦ともに国民年金に26年間加入していますが、ここ2年間は経済的に苦しく保険料の全額免除申請をし、保険料を払っていません。遺族年金は受けられないのでしょうか。
-
遺族基礎年金は、国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給権のある人が死亡した場合、死亡した人に生計維持されていた「子のある配偶者(夫あるいは妻)」または「子」に支給されます。
*かつては「子のある妻または子」でしたが、2014年度改正により「子のある配偶者または子」となりました。
ただし、子は18才未満(18歳に到達した年度の末日・3月31日まで)、または20才未満で1級・2級の障害の子に限られます。あなたの夫は加入中の死亡で、中学生の子がいるので該当します。
加入中の死亡の場合、死亡日の前に被保険者期間の1/3以上の保険料未納が無い、もしくは死亡した月の前々月までの1年間に未納がなければ支給されます。
最近の2年間は全額免除ということなので、遺族基礎年金を受給できるでしょう。全額免除は保険料を払っていなくとも「未納」ではないからです。
年金額は、基本額779,300円と子1人分の加算額224,300円の合計で約100万円ほどとなり、次男の高校卒業時まで(障害に該当する場合は20才になるまで)支給されます。その後は遺族基礎年金の受給権はなくなりますが、あなたが60歳になれば寡婦年金を受給できるでしょう。
寡婦年金とは、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含まれる)が25年以上ある夫が死亡した時、10年以上婚姻関係のあった妻に対して、(夫に障害基礎年金の受給権がなければ)60才から65才になるまでの間支給されます。金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の3/4となります。
市区町村の窓口または年金事務所で確認し、60才になった時に忘れずに請求しましょう。
相続について
同胞の法律はどこの法律が適用される?
「相続は被相続人(死亡した人)の本国法に拠る」のが国際私法上の原則です。日本に住んでいるからといって日本の法律が適用されるわけでもなく、また相続人の国籍などは関係ありません。
在日同胞の場合、
①朝鮮民主主義人民共和国(以下、共和国)の法を本国法とする人
②韓国法を本国法とする人
③「帰化」して日本国籍になった人
この3通りが考えられます。特別永住者証明書や在留カードに記載されている国籍表示で本国法が決まるわけではありません! では、どのように本国法は決まるのでしょうか?
それは、被相続人(死亡した人)の帰属意識、所持している旅券、渡航歴、所属する民族団体、親族との繋がり……などを斟酌して総合的に判断され、被相続人ともっとも密接な地域の法が本国法となります。
その本国法に基づいて、実際に相続で適用される法律は、
①共和国法を本国法とする人の場合は、共和国の対外民事関係法の規定により日本法
②韓国法を本国法とする人の場合は、韓国法
③「帰化」した日本国籍者の場合は、日本法
となります。このように、在日同胞の相続では、日本が適用される人と韓国法が適用される人がいます。
[ワンポイント] 日本法と韓国法の違い
前ページでは、同胞の相続では、日本法が適用される人と韓国法が適用される人がいると説明しました。
では、韓国法と日本法ではどのような違いがあるのでしょうか?まずは、①相続人の順位と相続人の範囲、②法定相続分に違いがあります。このほか、相続放棄、遺留分や寄与分の請求などにおいて違いがあります。
相続人の順位・範囲・ 相続分で日本法と韓国法を比較すると……
日本法
配偶者は同順位
①子……………相続分の1/2,配偶者は1/2
②直系尊属……相続分の1/3,配偶者は2/3
③兄弟姉妹……相続分の1/4,配偶者は3/4
韓国法
配偶者は同順位
①子や孫(直系卑属)
②父母や祖父母(直系尊属)
①または②の相続分1に対し、配偶者1.5
③兄弟姉妹 *配偶者がいない場合
④4親等以内の傍系血族 *配偶者がいない場合
例えば、妻と子が相続人の場合、日本法では妻の相続分は常に2分の1ですが、韓国法では妻は子の相続分の 1.5倍(5割増し)であるため、韓国法では、子の数が多ければ多いほど妻の相続分が少なくなります。
韓国法では相続人の範囲が広く、代襲相続の場合、子の配偶者(嫁や婿)も相続人になりますし、甥・姪・従兄弟姉妹・叔父叔母も相続人となる場合があります。
では、法定相続分における違いを具体的にみてみましょう。大きく異なるのは、配偶者の相続分です。
例えば、亡夫の財産100万円を妻と子が相続する場合でみてみます。
①日本法では、配偶者は2分の1、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。
例1)子が2人の場合、
妻は2分の1の50万円、子は残りの2分の1を2人で分けるので、子1人は4分の1の25万円ずつとなります。
例2)子が3人の場合
妻は2分の1の50万円、子は残りの2分の1を3人に分けるので、子1人は6分の1の16万5千円ずつとなります。
②韓国法では、配偶者の相続分は、子1人の相続分の1.5倍(5割増し)となります。
例1)子が2人の場合、
妻:子:子=1.5:1:1となり、妻は7分の3、子は7分の2ずつとなります。よって、妻は43万円、子は29万円ずつとなります。
例2)子が3人の場合
妻:子:子:子=1.5:1:1:1となり、妻は9分の3、子は9分の2ずつとなります。よって、妻は33万円、子は22万円ずつとなります。
韓国法では、配偶者の相続分が常に2分の1保障される日本法とは異なり、子の数が増えるほど妻の相続分が少なくなります。
親が負債を残して亡くなったとき・・・
相続は、被相続人の死亡により始まります。被相続人が持っていたすべての権利・義務、プラスの財産とマイナスの財産、すなわち負債も含めたすべての財産は相続人に移転することになります。その時、相続人は、相続を承認するのか、拒絶するのかを決めることができます。
承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。単純承認は、相続人が全ての財産の相続を無条件に承認することで、限定承認は、相続人が相続により得たプラスの財産の限度内で負債を弁済するという条件付きで承認をすることです。
これにたいし、相続放棄は相続の開始によるすべての財産の相続を拒絶するというものです。プラスの財産が無く、莫大な負債だけがあるような場合、相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄は日本法でも韓国法でも「相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内」に「裁判所」で「放棄の申述」をすることにより行います。
ここで言うところの「裁判所」は、財産所在地の裁判所です。
日本にある負債については亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。韓国国内にある負債の放棄については、被相続人の登録基準地(旧本籍地)にかかわらず、一律ソウルの家庭法院です。相続放棄の申述の効力はそれを行った国内のみで有効となりますので、日本で行った放棄の申述は韓国国内には及びません。
相続税が払えない
相続税の納付期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10カ月以内です。
そこで、相続税が払えない場合、大きく二つの方法があります。
①相続の放棄
②相続税の納税―イ・延納(金銭による分割納付)、ロ・物納(金銭以外の相続財産による一括納付)
相続税の納税は原則、金銭による一括納付です。金銭による一括納付が難しい場合に、例外として延納と物納が認められています。
1. 延納
下記の要件に従い20年以内の期間で年賦により納付することができます。この延滞期間中は利子税の納付が必要となります。
[要件]
イ 相続税額が10万円を超えること
ロ 金銭で納付することが困難で、その納付を困難とする金額の範囲内であること
ハ 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、延納税額が100万円以下で延納期間3年以下の場合は不要
二 相続税の納期限までに「延納申請書」「担保提供関係書類」を税務署長に提出すること
2. 物納
延納によっても金銭で納めることが困難な場合、納付期限までに「物納申請書」「物納関係書類」を税務署長に提出することによって物納が認められます。
物納申請財産には順位があります。第1順位は不動産、上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産となります。
*延納・物納申請は同時に行えます。申告期限後であっても、物納から延納への変更申請は可能です。
生前の相続対策は?
相続税の節税対策に生前贈与を活用しよう。
相続税の節税対策には、相続財産の評価額を下げる方法などいろいろありますが、生前贈与をうまく活用して、相続時の財産総額を減らすのも有効な方法です。
また、生前贈与は相続人以外の人にもできるので、例えば世代を超えて孫へダイレクトに財産を贈与すれば、相続税の二世代課税の回避にもつながります。
一般的な贈与税(暦年課税)のしくみは基礎控除額(暦年110万円)を超える金額に税率をかけて計算します。
年間110万円までなら無税なので、実効税率は0%です。
例えば200万円の暦年贈与の場合、贈与税が9万円、この場合の実効税率は4.5%になりますが、その人の相続財産から計算した相続税の実効税率より低ければ、贈与をすることによって相続税の節税になります。
毎年少しずつ贈与するのも良いですが、連年贈与の場合は注意が必要です。
例えば毎年20年間 に渡って年100万円を贈与するという贈与契約をした場合だと、契約年に2000万円の定期金の贈与をしたとみなされて、多額の贈与税が発生します。
毎年贈与する場合でも、贈与の都度贈与契約書を作成し、銀行振込などでお互いに履歴を残すようにしましょう。
また、贈与とは、贈与者と受贈者の意思確認があって成立する契約なので、贈与契約書には受贈者が必ず直筆でサインしておきましょう。
さらに贈与を受けた財産は、受贈者のものであること、つまり受贈者が管理していつでも受贈者が使える状態であるということが大切です。
基礎控除額を超えた贈与で、贈与税の申告をしていれば一つの証拠としては有効ですが、申告書だけでは贈与が認められなかったケースもあります。
暦年課税以外にも住宅資金や結婚子育て資金、教育資金の贈与の非課税制度があるので、上手に使い分けてください。
最後に相続税時精算課税を利用する贈与制度がありますが、相続時精算課税制度を選択した受贈者は、同一の贈与者から受ける翌年以降の贈与については、贈与税の基礎控除110万円が使えなくなるので注意してください。
相続手続きに必要な書類
相続による名義変更等に必要な書類は概ね下記のとおりです。
1)被相続人の閉鎖された外国人登録原票と住民票の除票
2)相続人全員の住民票
3)
・被相続人が朝鮮籍の場合
朝鮮総聯発行の相続証明書(最寄りの総聯本部にて申請)
・被相続人に南の故郷に家族関係登録簿がある場合
被相続人の出生から死亡の事実が記載された除籍簿謄本、家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書
4)遺産分割協議書
*相続人全員が署名・実印にて押印
5)財産目録
*土地・建物の登記簿謄本添付(法務局にて交付)
*土地・建物の評価証明書(市町村役場にて交付)
*固定資産税の納税通知書
6)相続人全員の印鑑登録証明書
7)相続人が他にいない旨の申述書
などです。不明な点があれば、いつでもセンターにご相談ください。
死亡した人の登録原票の取り寄せ
新在留管理制度が施行され、外国人登録原票は閉鎖されました。
施行以前、外国人登録原票は住所地の市町村役場で管理していたのですが、外国人登録制度の廃止に伴い、法務省が全国の市町村から登録原票を回収し、「閉鎖登録原票」として一元管理しています。
センターによくある相談に、「閉鎖された登録原票の取り寄せはどうすればいい?」というものがあります。
例えば、遺族年金の申請や父母が死亡して相続手続きをする際に、配偶者であることの証明や相続人を確定するための資料として、あるいは住所地の変遷や在留資格の変更の履歴を証明するために必要になることがあるからです。
自分の閉鎖登録原票の写しを請求したい場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に拠り、法務省にたいして開示請求することができます。 ところが、この個人情報保護法が対象にしている『個人情報』は、生存している人に限られます。そのため、死亡した人の原票は請求の対象にはなりません。
では、死亡した人の登録原票はどうすればよいのでしょうか?死亡した人の登録原票の写しの請求の方法には2通りあります。
①死亡した人の原票に自分の情報が含まれている場合(例えば、死亡した人が自分の父母で、子が死亡した父母の原票を請求したい場合)、今述べた個人情報保護法にもとづき、開示請求を行うことができます。
但し、この場合、自分の情報に関連する部分に限定されるので、死亡した人の原票全ては開示されませんが、(死亡した人が世帯主であった場合は)備考欄に配偶者や子などの家族構成員を確認することが可能です。
請求の方法は、原則として郵送による請求で、①開示請求書(法務省のHPからダウンロード、手数料の欄に300円分の収入印紙を貼付)、②請求人の本人確認書類(住民票の写しなど)、③返信用の封筒(90円切手貼付)、開示請求書の郵送先は、
法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
03-3580-4111(内線2034)
100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
②行政サービスによる写しの交付申請ができます。
この場合、その死亡した人の登録原票にある、死亡した人と請求をした人の情報のみが提供され請求人以外の者に関する情報が含まれている場合はその部分が黒く消除されます。
この場合、死亡した人の原票全てが開示されますが、請求人以外の者の事項はすべて黒く消除されるため、①のように家族事項を確認することはできません。請求人は、死亡した人と(死亡当時)同居していた親族、死亡した人の配偶者(内縁の妻を含む)、直系尊属、直系卑属または兄妹姉妹、これらの法定代理人です。
請求の方法は、原則として郵送による請求で、①交付請求書(法務省のHPからダウンロードできます)②請求人の本人確認書類(住民票の写しなど)、③返信用の封筒(90円切手貼付)
交付請求書の郵送先は、法務省入国管理局出入国管理情報官室 03-3580-4111出入国情報開示係100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
各種の手続きで死亡した人の登録原票の写しが必要な場合、上記の①、②のいずれかあるいは両方の場合で申請することになります。
*上記の①,②では請求先が異なります。不明な点については、センターまでご連絡ください。
相続放棄と生命保険
- 2カ月前に父(朝鮮籍)が死亡しました。飲食店を経営していた父にはかなりの負債があり、到底返済できそうにありません。相続人は母と私、そして弟で、自宅もあきらめ相続放棄をするつもりです。母から亡父が1千万円の死亡生命保険に加入していたことを聞きました。生命保険金も放棄しなければならないのでしょうか?
-
生命保険金は基本的には相続放棄の対象にはなりません。なので、負債も含めて亡父の全ての財産を放棄しても保険金を受け取ることはできます。
この事例のように、相続人が相続放棄をした場合については、相続人は相続放棄をしても保険金請求権を失うことはありません。
保険金請求権は相続財産に属さず、保険事故発生時、すなわち死亡時における相続人=受取人の固有財産になると解されているからです。相続放棄は死亡した父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄の申述」という手続きを行います。申述書は裁判所に備置されています。
遺言のすすめ
相続で兄弟姉妹らがもめにもめ、まさに「争続」になってしまうことはよくあること。争いを避けるためにも有効なのが遺言。
遺言の方式は幾つかあります。その中でも専門家がお勧めするのが公正証書遺言です。数万円、資産の多い人なら 10万円以上の費用がかかりますが、公証人役場にて行うこの遺言の方法だと、相続開始時、つまりは遺言執行時の手続きが他の方式と比べてはるかに簡素化されます。また遺言の内容などに不備があり無効になるという心配もありません。遺言書も公証人役場で保管してくれます。ただし、立会人(証人)2名が
必要になります。
自筆証書遺言の方式は、その遺言書が作成者本人がお亡くなりの後、相続人がその遺言書が保管場所を知らないため発見されないとか、自分に不利になると考えた相続人がそれを握りつぶすといったことも起こりかねません。その遺言書の管理を任された相続人が他の相続人からあらぬ疑いの目で見られる、というのもよくある話です。
また、書き方をよく知らないまま作成すると内容に不備があるということで無効になってしまいかねません。さらには遺言内容を執行するにおいて家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(遺言の有効・無効を判断する手続ではない)。この検認の前に封を開けてしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。
※こんな場合、遺言(自筆証書遺言)は無効になります。
×ワープロで作成した
×作成日を「1月吉日」というような特定できない日付にした(遺言は後に作成されたものが優先されるので曖昧な日付は駄目です)
大切な人がなくなったら
家族が亡くなったら…死亡届・埋葬許可
親や家族が亡くなると悲しみに浸る間も無く、葬儀の準備などでバタバタします。しかし、人の死亡後には様々な手続きが必要で、その中には短い期限内に急いで行わなければならないものがあります。
まずは死亡届です。死亡した日から7日以内に最寄りの市区町村役場に提出します。その場合、医師による死亡診断書(または警察による死体検案書)と届出人の印鑑が必要です。届出は、親族(同居していなくてもよい)、同居人、家主や地主などで、葬儀を業者に依頼する場合は代理で届出をしてくれます。
これと同時に、埋葬許可申請も行います(死亡届が受理されないと埋葬許可書は発行されず、これが無ければ、葬儀も火葬もできません)。
年金支給の停止
65歳以上で、老齢年金を受給していた親が亡くなった場合、死亡後速やかに年金支給停止の手続きを行う必要があります。
親が老齢基礎年金(国民年金)を受給していた場合は、死亡後 14日以内に、老齢厚生年金の場合は10日以内に、市区町村役場の国民年金課、または最寄りの年金事務所で手続きを行います。その際、亡くなった親の年金証書、住民票の除票、年金受給権者死亡届などが必要になります。
また、亡くなった親が要介護認定を受けていた場合は、死亡から14日以内に、介護保険者証を返還しなければなりません。手続きは、亡くなった親の住所地の市区町村役場の高齢福祉課などの窓口で、必要なものは、介護保険証と介護保険資格喪失届(窓口にあります)です。
[ワンポイント] 除票って?
死亡届を提出すると、住民基本台帳から抹消されます。住民登録が抹消された住民票を「除票」と言います。死亡生命保険金をはじめ死亡後の各種の手続きに際し、提出を求められる場合があります。
[ワンポイント] 世帯主の変更
亡くなった親が世帯主であった場合、同じ世帯に 15歳以上の者が2人以上いる場合、世帯主の変更届も必要になります。死亡後、14日以内に住所地の市区町村役場の市民課で手続きします。本人確認のための身分証明書と印鑑が必要です。
このような手続きの他、相続税の申告は、死亡した日の翌日から10カ月以内、生命保険金の請求は、死亡から2年以内です。
未支給年金の請求
亡くなった親が老齢年金を受給していた場合、親族が請求することができます。
年金は受給者が死亡した月の分までが支払われますが、年金の支払いは後払いで、偶数月の15日にその前の2カ月分がまとめて振り込まれます。例えば、親が7月に死亡した場合、4月、5月分は6月15日にすでに支払われているため、6月分と死亡した月である7月分の年金が未支給年金になります。
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった親と死亡した当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。
年金事務所に「未支給年金請求書」を提出します。また、別世帯であっても、身の回りの世話やお見舞い、葬儀の費用を出したなど、なんらかの経済的な援助をしていたような関係があれば、「生計同一」と認められます。「請求書」の提出時に「生計同一に関する申立」を行います。
未支給年金~こんな事例
- 11月20日、アボジが80歳で亡くなりました。オモニは数年前に亡くなっており、娘の私が近くに住んでいるので、アボジは一人で暮らしていました。アボジの年金を止める手続きのため年金事務所に出向いたところ、「未支給年金が請求できますよ」と言われました。未支給年金とは何ですか? 結婚して別に住んでいる娘でも請求できるのでしょうか?
-
未支給年金とは、年金を受給している人が亡くなった時、その人が受け取っていない年金のことを言います。
年金は受給者が死亡した月の分までが支払われるので、アボジは11月分まで年金を受給できます。
しかし、年金の支払いは後払いで、偶数月の15日にその前の2か月分がまとめて振り込まれます。アボジの8月、9月分の年金は10月15日にすでに支払われているので、10月分と亡くなった11月分の年金が未支給年金となります。
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人が死亡当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。年金事務所に「未支給年金請求書」を提出します。
でも、この事例では、娘さんは亡くなったアボジの子ではあるものの別世帯です。請求はできるのでしょうか?
たとえ、別世帯であっても、日常的に連絡をとっていたり、身の回りの世話やお見舞い、葬儀の費用を出したなど、なんらかの経済的な援助をしていたような関係があれば、「生計同一」と認められます。「請求書」の提出時に「生計同一に関する申し立て」を行います。この時、第3者による証明が必要ですが、3親等内の親族以外で、近所の人や親子の日常的な関係をよく知る人であれば大丈夫です。
埋葬料・埋葬費、葬祭費の請求
健康保険に加入している人やその扶養家族が亡くなった時、加入していた健康保険組合や協会けんぽに健康保険証を返納し、埋葬料等の請求の手続きをします。加入していた人(被保険者)が死亡し、葬儀を行った家族に支給されるお金を「埋葬料」と言い、加入者していた人の扶養家族が死亡した時、加入者に「家族埋葬費」が支給されます。いずれも一律 5万円が支給されます。申請先は加入していた健康保険組合や協会けんぽです。
国民健康保険の場合、扶養の有無に関わらず「葬祭費」が支給されます。「葬祭費」は地方自治体ごとに金額が異なります。申請先は亡くなった人の住所地の市区町村役場です。
上記のいずれも葬儀を行った場合に支給され、葬儀を行った日から2年以内に申請します。
大切な人が亡くなった後の手続きあれこれ
センターに寄せられる相談で一番多いのは相続に関するものです。遺産分割協議から相続放棄までその内容は様々です。
しかし、どこの家庭にでも必ず相続は「問題」になるということでもありません。また、すぐに対処あるいは解決しなければならないわけでもなく、亡くなった人に負債などが無い限りは、しばらくそのままにしておいてもよい場合もあります。
家族が亡くなった後、その人に関連する幾つかの法律上の手続きが必要ですが、すぐに行うものと、一定の期間内にすべきもの、相続が確定した (遺産分割合意が整った) 後に行うものがあります。
例えば・・・・
・死亡届:死亡した日から7日以内
・世帯主の変更:死亡後、2週間以内
・電気・ガス等の公共料金:名義の変更はなるべく早い目に
・年金支給の停止:死亡した親が老齢基礎年金を受給していた場合は2週間以内、老齢厚生年金の場合10日以内
・死亡一時金や遺族年金の請求:死亡後5年以内、但しなるべく早く
・埋葬費:2年以内
・死亡した人の高額療養費の還付請求:2年以内
・相続税:10ヶ月以内
・死亡生命保険金の請求:3年以内
・不動産の名義変更:相続人が確定し遺産分割協議が整った後
・預貯金の解約:相続人が確定し遺産分割協議が整った後
・株券の名義変更:相続人が確定し遺産分割協議が整った後
・・・・・・・・・・などなどです。
とんぽらいふ – 在日同胞のための生活便利帳
http://tonpo-center.com/tonpo-life/(引用 2024-3-5)
.png)